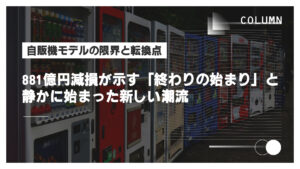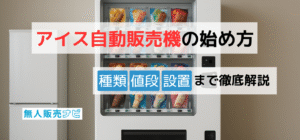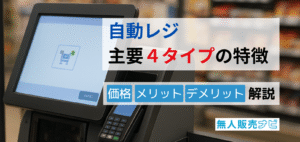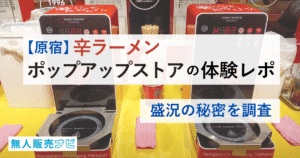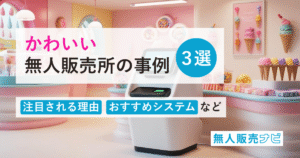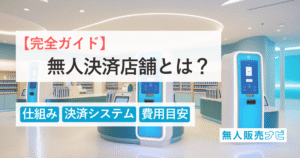「野菜を無人販売してみたいけど、何から始めたらいいか分からない」
「おすすめの自販機や初期費用、補助金について知りたい」
「儲かるのか、失敗しないためのコツを先に押さえておきたい」
このようにお考えではないでしょうか?
結論から言うと、野菜を無人販売する方法は以下の通りです。
- 必要なスペース・電源・防犯条件を確認
- 野菜の無人販売に必要な許可を取得
- 自販機を選び、予算・仕入れ方法を決める
- 決済方法(現金やQRコードなど)・運用体制を整備して販売開始
本記事では、野菜を無人販売するために必要な準備や許可、自販機の選び方から実際の運用開始までをステップ形式で解説します。
さらに、初心者にもおすすめの自販機3機種や補助金制度、利益シミュレーションまで網羅しています。
この記事を読めば、野菜の無人販売に必要な条件が分かり、採れたて野菜の無人販売を始められます。
ぜひ最後までご覧ください。
24時間 無人で運営可能
国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し
- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応
- テック業界初!3つの物体識別方式を統合
野菜の無人販売・無人八百屋の仕組みとは?

野菜の無人販売とは、販売員を置かずに野菜を売る仕組みのことです。
主な無人販売・無人八百屋の形式は以下の通りです。
- お賽銭箱タイプの無人販売所
- ロッカー型自販機
- スマート販売機
無人販売の起源こそ明確ではありませんが、日本では太平洋戦争前から存在しており、「良心市(りょうしんいち)」という名で知られていました。
その名の通り、「買う人の良心」に委ねる性善説に基づいた仕組みでしたが、時代とともに盗難被害が増加。
参考:wikipedia
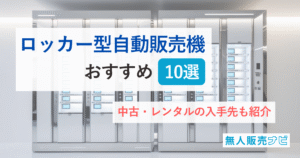
野菜を無人販売する方法|準備~運用開始

本章では、野菜を無人販売する方法について準備~運用開始までを解説します。
- 必要なスペース・電源・防犯条件を確認
- 野菜の無人販売に必要な許可を取得
- 自販機を選び、予算・仕入れ方法を決める
- 決済方法(現金やQRコードなど)・運用体制を整備して販売開始
必要なスペース・電源・防犯条件を確認
無人で野菜を販売するには、まず「設置できる場所があるかどうか」を確認することから始めましょう。
以下の3点は最低限チェックしておくべきです。
| チェックポイント | 詳細 |
|---|---|
| 設置スペース | 幅1〜2m・奥行50cm程度が目安。 雨風を防げる屋根付きや軒下が理想。 |
| 電源(100V) | 冷蔵機能付きやキャッシュレス決済に対応する自販機には家庭用電源が必要。 |
| 防犯対策 | 人通りの多い場所、明るい照明、防犯カメラの設置が安全確保に役立つ。 |
例として、マンションの出入口や、農産物直売所の一角などは防犯と集客の両面で好条件といえるでしょう。
野菜の無人販売に必要な許可を取得
野菜を販売するときには、場合によっては「許可」が必要になります。
特に加工品(カット野菜や漬物)を売る場合や、公共の場所を使う場合には注意が必要です。
基本的に、生の野菜をそのまま売るだけであれば、保健所への許可は不要とされています。
自販機を選び、予算・仕入れ方法を決める
販売場所や予算に応じて、どのタイプの無人販売機を使うかを決めましょう。
野菜の無人販売に使える自販機は、大きく分けて以下の3タイプです。
| 形式 | 特徴 |
|---|---|
| お賽銭箱スタイル | ・コンセント不要で、棚と料金箱を置くだけ ・1万円前後で導入可能 ・現金盗難リスクがあり、無人環境では注意が必要 |
| ロッカー型販売機 | ・各商品ごとに個別ロックが可能 ・保冷機能付きのタイプもあり、ドリンクやスイーツの販売も可 ・1枠ずつ異なる金額で販売でき、自由度が高い |
| スマート自販機 | ・キャッシュレス決済対応 ・遠隔操作で在庫・売上管理ができ、補充のタイミングも把握可能 ・液晶で販促動画や広告を表示でき、通行人への訴求力が高い |
自分の畑で育てた野菜を売ってもいいですし、地元の農家と提携して仕入れる方法もあります。
「どこから仕入れて、いくらで売るか」を最初に決めておくと、利益が出るかどうかが見えやすくなります。
決済方法(現金やQRコードなど)・運用体制を整備して販売開始
自販機の準備が整ったら、次は「どうやってお金を受け取るか」を決めましょう。
以下の表に、代表的な決済方法とメリット・デメリットをまとめました。
| 決済方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現金 | ・導入コストが低い ・高齢者にも使いやすい | ・盗難リスクあり ・釣り銭対応が面倒 |
| キャッシュレス | ・盗難の心配が少ない ・24時間無人対応が可能 | ・初期費用がかかる ・利用者側に使い慣れていない人もいる |
販売開始後は、以下のような運用が必要になります。
- 野菜の補充や入れ替え
- 売上や在庫のチェック
- 清掃やメンテナンス
最初は品数を絞ってスタートし、徐々に売れ筋やお客様の声を反映させていくと、安定した運営につながるでしょう。

野菜の無人販売におすすめの自販機3選|価格や機能性を比較

本メディア編集チームがおすすめする「野菜の無人販売機」は以下の通りです。
今回は、以下の点を選定基準としてピックアップし、それぞれの機種を評価させていただきました。
- 鮮度維持
- 運営容易性
- 初期費用
- 販売機能
- リスク低減
次章では、各無人販売機の詳細を解説します。
スマリテ|遠隔操作・自動決済・おしゃれなラッピング対応

| 鮮度維持 | ・3温度帯対応(常温/冷蔵/冷凍) ・HACCP準拠(無人販売機として国内唯一) ・賞味期限監視と自動販売停止 |
|---|---|
| 運営容易性 | ・アプリによる自動個人認証→商品識別→自動課金(扉閉め5秒で決済) ・クラウドで遠隔操作・価格変更・動画配信・開閉制御が可能 |
| 初期費用 | ・【A】ハカリ方式:85万円〜(冷凍・冷蔵・常温/520L) ・【B】ICタグ方式:85万円〜(冷蔵・常温/566L) ・【C】ハカリ方式:58万円〜(冷蔵・常温/520L) |
| 販促機能 | ・サイネージ対応(大画面液晶ディスプレイで動画配信) ・クーポン発券機能 |
| リスク低減 | ・賞味期限切れ→自動アラート+販売停止 ・商品未回収(盗難)リスクゼロ(扉開閉記録&課金連動) |
スマリテは「商品検知システム」と「クラウド遠隔機能」を搭載する最新機能が詰まったスマート自販機です。
野菜を取るだけで自動的に決済されるため、盗難の心配がほとんどありません。
おしゃれなラッピング対応で見た目のインパクトも抜群。SNS映えも狙えます。
24時間 無人で運営可能
国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し
- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応
- テック業界初!3つの物体識別方式を統合
自動販売機JP|21マス収納&保冷対応、選べる2タイプ
| 鮮度維持 | 冷蔵機能により、外気の温度や湿度に左右されずに野菜の鮮度を保持 |
|---|---|
| 運営容易性 | 24時間365日の無人販売が可能 |
| 初期費用 | 要問い合わせ ※初期費用0円のリースプランを提供 |
| 販促機能 | オプションでオリジナルデザインラッピングが可能 |
| リスク低減 | 屋外設置に対応しており、従来の直売所や無人販売所で見られる商品や現金の盗難リスクを軽減 |
「自動販売機JP」が提供する野菜販売用自販機は、ロッカー型と食品汎用型の2タイプがあり、屋外設置にも対応しています。
ロッカー型は最大21マスの収納スペースがあり、大きめの野菜(キャベツや白菜)もラクに入れられます。
一方、食品汎用型は保冷機能が付いており、鮮度が気になる葉物野菜にも最適です。
NTTアグリテクノロジー|初期費用ゼロで導入できる収納21口のロッカー型

| 鮮度維持 | ・無電源の常温ロッカー型 ・冷蔵機能付きタイプも用意あり(要問い合わせ) |
|---|---|
| 運営容易性 | 軒先販売を想定し、設置申請不要の場所で導入可能(要確認) |
| 初期費用 | 初期費用不要、売上連動の手数料制 |
| 販促機能 | POP作成や価格設定サポートあり(ラッピングやサイネージなど高度な販促機能はなし) |
| リスク低減 | 現金回収型の無人販売に比べて、農作物や金銭の盗難リスクを大幅に削減 |
NTTアグリテクノロジーの提供する野菜自販機は、初期費用不要で売上に応じて課金されるため、経済的負担を抑えられるのが特徴です。
ロッカー型で21マスの収納があり、価格も100円〜600円の間で自由に設定できます。
販売機の見た目はシンプルですが、コストを最優先したい方には十分な機能が揃っています。

野菜の自動販売機に活用できる補助金・助成金制度

自販機を導入したいけど、初期費用がネックなときに頼れるのが「補助金・助成金制度」です。
以下に、実際に活用できる代表的な制度をまとめました。
| 補助制度名 | 対象者 | 補助内容 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業等で20人以下の小規模事業者 | 販路開拓や業務効率化のための経費(機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費など | 最大50〜100万円(2/3補助) |
| 省力化投資補助金 | ・中小企業者 ・小規模企業者 ・小規模事業者 ・特定非営利活動法人 ・社会福祉法人など | IoT・ロボット等のデジタル技術を活用した省力化設備の導入 | ・補助金額1,500万円までは1/2(小規模・再生事業者は2/3) ・1,500万円を超える部分は1/3 ・補助上限額は従業員数に応じて最大1億円 |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 中小企業等で、3~5年の事業計画を策定・実施し、付加価値額や給与支給総額の年平均成長率などの要件を満たす者 | ・革新的な製品・サービスの開発 ・生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等 | ・中小企業は1/2 ・小規模企業・再生事業者は2/3 ・補助上限額は従業員数に応じて最大2,500万円 |
| 東京都 食品ロス削減補助金 | 東京都内で店舗を運営する食品小売事業者 | ・食品ロス削減に資するシステムや機器の導入 ・フードバンクへの寄贈に係る輸送費支援など | ・原則1/2(フードバンク寄贈の輸送費は10/10) ・補助上限額は1事業者あたり1,500万円。 |
これらの制度のうち、とくに「東京都 食品ロス削減補助金」は、野菜や総菜などの鮮度管理が重要な商品を扱う無人販売機との相性が非常に良いのが特徴です。
たとえば、スマリテはこの補助金制度に完全対応しており、食品ロス削減の具体的な対策機器として東京都からも高く評価されています。
実際、スマリテを導入した事業者では賞味期限切れによる廃棄が平均70%削減されたという報告もあり、補助金活用と業務改善の両立を実現しています。

野菜を無人販売する4つのメリット

本章では、野菜を無人販売する4つのメリットを解説します。
- 販売員不要で人件費を大幅カットできる
- 無人運営で昼夜問わず24時間販売できる
- 収穫直後の野菜をそのまま販売できる
- 規格外野菜も売れるため、食品ロスの削減に直結する
販売員不要で人件費を大幅カットできる
無人販売の最大の魅力は、「人手がいらないこと」です。
通常のお店なら、レジ・接客・在庫チェックなどにスタッフが必要で、毎月の人件費が大きな負担になります。
ところが、自販機なら販売はすべて自動であり、やることは野菜の補充とカゴの掃除くらいなので、1人でも無理なく続けられます。
人手不足に悩む地域でも、ムリなく始められます。
無人運営で昼夜問わず24時間販売できる
無人販売機は24時間365日ずっと働き続けてくれます。
お店のように営業時間を決める必要がないため、夜中でも朝方でも、買いたい方が自由に購入できます。
早朝の農作業帰りに新鮮な野菜を買う方や、仕事終わりの遅い時間に立ち寄る共働き家庭など、時間帯に関係なく販売可能です。
収穫直後の野菜をそのまま販売できる
無人販売なら「朝収穫して、昼には販売機に並べる」といったスピード感で動けます。
スーパーに野菜を並べるには、収穫後に出荷して、業者が運び、店頭に並ぶまでに1〜2日かかることもあります。
その間に鮮度が落ちてしまうのが欠点です。
規格外野菜も売れるため、食品ロスの削減に直結する
無人販売なら、規格外野菜も「味は同じ」「安くてお得」として並べられます。
規格外野菜は、形が曲がっていたり、サイズが不揃いだったりするだけで、まだ食べられるのに捨てられてしまうのが悩みのタネです。
ところが、ちょっと見た目が不格好なだけで、味や栄養に変わりはありません。

野菜を無人販売する3つのデメリット

本章では、野菜を無人販売する3つのデメリットを解説します。
- 現金や野菜の盗難リスクがある
- 売り場で声かけできず販促力が低下しやすい
- 数万円~数十万円の初期費用がかかる
現金や野菜の盗難リスクがある
無人販売には、誰でも気軽に買えるメリットがある反面、「盗まれてしまうかも」というリスクもあります。
とくに昔ながらのお賽銭箱式スタイルでは、現金がそのまま置いてあるため、心ない人に持ち去られることも。
また、夜間や人通りの少ない場所に設置すると、野菜そのものが盗まれてしまうケースもあります。
こうしたリスクを減らすためには、次のような対策が効果的です。
- 鍵付きのロッカー型自販機を使う
- 防犯カメラや照明を設置する
- QRコード決済など現金を使わない方法にする
売り場で声かけできず販促力が低下しやすい
無人販売は便利な反面、「いまが旬ですよ!」「今日のおすすめです!」といった声かけができません。
普通のお店のように接客ができないため、お客さんに商品の魅力を伝えるチャンスが少なくなります。
たとえば、
- どんな味なのか分からない
- 使い方や保存方法が伝わらない
- ついで買いが起こりにくい
といった課題が出てきます。
これを補うには、以下のような工夫が効果的です。
- 商品に説明カードやおすすめレシピを添える
- 季節感あるポップで目を引くようにする
- スマート販売機の画面で動画やメッセージを流す(サイネージ機能)
売り手の「想い」を形で伝えることが、無人でも売上アップにつながります。
数万円~数十万円の初期費用がかかる
人件費がかからないのが無人販売の魅力ですが、自販機本体だけでも次のような金額がかかります。
| 無人販売のタイプ | 初期設置費用 | 費用名目 |
|---|---|---|
| お賽銭箱の無人販売所 | 数万円~約10万円 | ・木材 ・組み立て費 ・監視カメラ等 |
| ロッカー型 | 無料~5万円 | 自販機購入費等 |
| スマート販売機 | 50万円程度 ※助成金利用可能 | ・システム導入費 ・自販機購入費等 |
無人販売の導入には初期費用がかかりますが、運営の省力化や中間マージンの削減により、費用以上の収益効果が期待できます。
例えば「スマリテ」は、規格外野菜の販売や流通コストの圧縮を実現し、初期費用を早期に回収できるモデルとして注目されています。
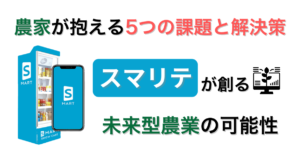
野菜の無人販売は儲かる?利益モデルと回収シミュレーション

野菜の無人販売は、やり方次第で儲けることは可能です。
以下では、ロッカー型の自販機を使ったシンプルな利益モデルを紹介します。
▼ロッカー型自販機の利益モデルと回収シミュレーション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 約30万円(本体・設置・電源工事含む) |
| 仕入れ価格(1袋) | 約100円(自家栽培 or 近隣農家と提携) |
| 販売価格(1袋) | 300円 |
| 1日の販売数 | 20袋 |
| 営業日数(月間) | 25日 |
| 売上(月間) | 300円 × 20袋 × 25日 = 150,000円 |
| 仕入れコスト(月間) | 100円 × 20袋 × 25日 = ▲50,000円 |
| 電気・通信費 | ▲5,000円 |
| 消耗品・販促費(袋・POPなど) | ▲5,000円 |
| 月間利益 | 約90,000円 |
| 回収までの目安期間 | 月9万円の利益 → 初期費用30万円なら約3.3ヶ月で回収可能 |

野菜の無人販売が注目される4つの背景

本章では、野菜の無人販売が注目される4つの背景を解説します。
- コロナ禍をきっかけとした無人販売の需要増加
- 野菜摂取や地産地消が支持され、健康志向が加速
- 食品ロスに対する関心
- おしゃれなロッカー型自販機の普及
コロナ禍をきっかけとした無人販売の需要増加
新型コロナの影響で「人と接しない買い物」を求める声が急増し、無人販売が注目を集める大きなきっかけとなりました。
「レジの行列を避けたい」「密を気にせず買い物したい」といった声から、スーパーに代わる“新しい買い方”として利用が拡大しました。
今では感染症対策だけでなく、買い物の効率や手軽さを評価する方が増えており、一時的なブームではなく“新たな生活スタイル”として定着しつつあります。
無人販売は、これからの時代にも合ったスマートな売り方として、今後も広がっていくでしょう。
野菜摂取や地産地消が支持され、健康志向が加速
「体にいいものを食べたい」「できれば地元の野菜を選びたい」という健康志向の高まりが、無人販売の人気を押し上げています。
無人販売では、農家さんがその日に採った野菜をそのまま並べられるので、スーパーよりも新鮮で安心感があります。
誰が作ったのか、どこで採れたのかが分かるのも嬉しいポイント。
食品ロスに対する関心
SDGsの普及に伴い、日本国内でも食品ロス削減への関心が高まっています。
実際に大手食品会社や小売業者によって、食品ロス削減に関する具体的な取り組みが進められており、その中でも「無人販売」という形態は注目を集めています。
無人販売では、通常の小売店では販売困難な規格外の野菜や、賞味期限が近いような商品も販売可能です。
おしゃれなロッカー型自販機の普及

従来の地味で簡易的な販売所に比べて、近年は木目調のパネルやカフェ風のラッピングが施された、見た目にもこだわった無人販売機が登場しています。
とくに都市部では、「地域のおしゃれスポット」として話題になる例もあり、販売台数を伸ばしている事例もあります。
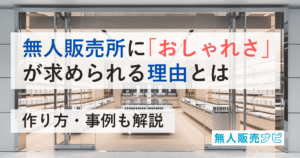
野菜の無人販売が失敗してしまう3つのケース

本章では、野菜の無人販売が失敗してしまう3つのケースを解説します。
- 人通りの少ない場所に設置してしまい売上が伸びない
- 見た目が悪い野菜ばかりで購入意欲が下がる
- 周辺相場を無視した価格設定で販売持続が困難になる
人通りの少ない場所に設置してしまい売上が伸びない
無人販売は立地次第で売上が大きく左右されます。
どんなに野菜の質が良くても、人目に触れない場所では「存在そのものに気づかれない」ため売上は伸びません。
住宅街の裏道や目立たない私有地では、せっかく設置しても通行量が少なすぎて成果につながらないことも。
安定して売れている自販機の多くは、以下のような立地にあります。
- コンビニやスーパーの近く
- 駅前やバス停周辺
- 道の駅・農産物直売所の敷地内
- 学校や幹線道路沿いの歩道沿い
設置前に「1日どれくらい人が通るか」を目視でカウントしたり、Googleマップのレビュー数などで周辺の流動人口を把握するのが効果的です。
見た目が悪い野菜ばかりで購入意欲が下がる
無人販売では、商品の第一印象が売上に直結します。
店員による声かけや説明がない分、見た目が悪いと「買いたい」という気持ちになりません。
規格外野菜を扱うのは魅力ですが、汚れすぎ・しおれ・変色などがあると、どんなに安くても敬遠されることがあります。
避けるべき状態の例は以下の通りです。
- 泥が大量に付着している
- 葉がしおれて元気がない
- 虫食いや変色が見られる
周辺相場を無視した価格設定で販売持続が困難になる
相場と合っていない価格設定は、売れ残りや赤字の原因になります。
たとえば、近くのスーパーでトマトが1袋150円なのに、自販機で300円で売っていたら、多くの方はその場で立ち去ってしまうかもしれません。
逆に安すぎると、利益が出ず長く続けられません。
販売を継続するためには、以下の行動が効果的です。
- 半径1km以内のスーパー・直売所で価格を調べておく
- 商品に「新鮮」「農家直送」「無農薬」など価値を伝えるポップをつける
価格だけで勝負せず、「なぜこの値段なのか」を説明する姿勢が信頼につながります。

まとめ
本記事では、野菜を無人販売する方法について解説してきました。
それでは、この記事の要点を振り返ってみましょう。
- 野菜の無人販売機を設置するには、幅1〜2mのスペース・家庭用電源・防犯対策が必要
- 生野菜のみなら許可は不要だが、加工品や公共地利用には申請が必要
- 自販機は予算や目的に応じて、お賽銭箱型・ロッカー型・スマート型から選べる
- 決済方法は現金かキャッシュレスを選択し、運用は補充・清掃・在庫管理が中心
- スマリテのような機種なら、防犯・販促・遠隔操作機能で初心者も安心
- 導入費用は補助金制度(例:東京都食品ロス補助金)で大幅に抑えられる
- 売上を伸ばすには、立地・野菜の見た目・周辺相場に合った価格設定が不可欠
- 月20袋販売できれば、初期費用30万円は約3ヶ月で回収可能な収益モデル
本記事を参考に、収益性と継続性のある無人販売を始めてみてください。
導入する販売機の選定に迷った場合は、「スマリテ」のような多機能型の無人販売システムがおすすめです。
東京都の食品ロス削減補助金を活用すれば、スマリテの導入費用を大幅に抑えることもできます。
ぜひお気軽にご相談ください。