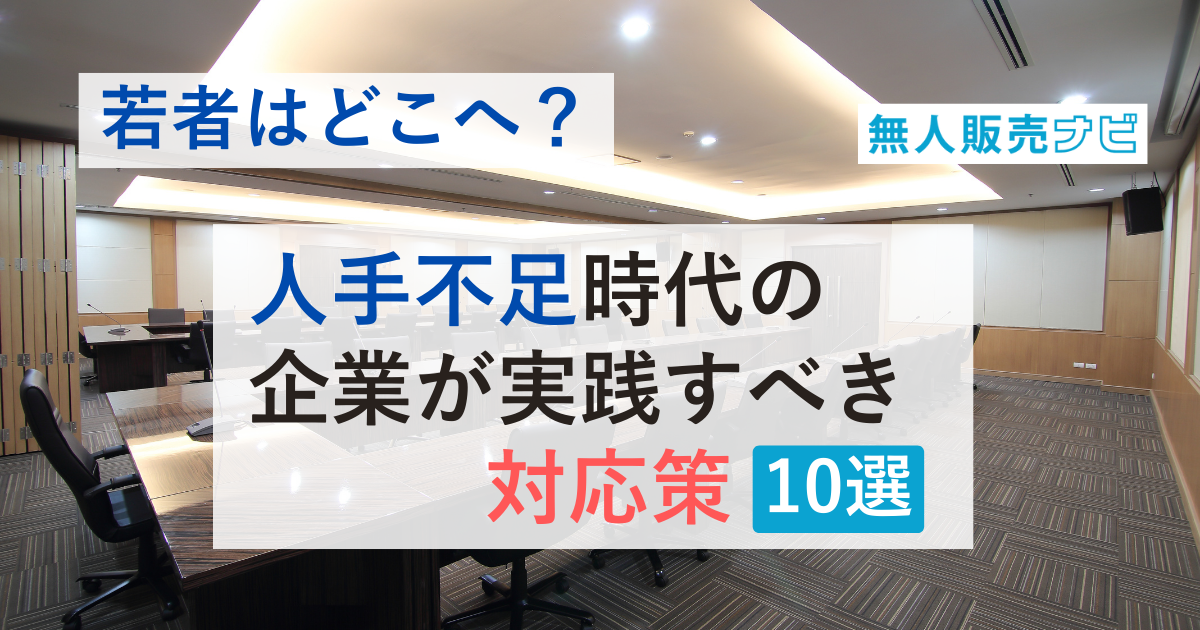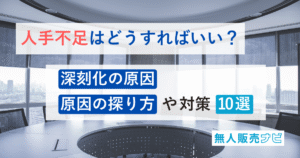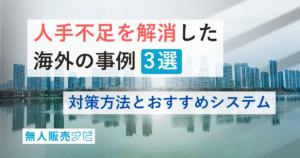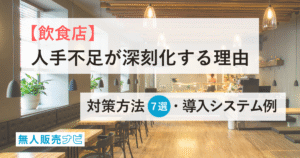「若い人が本当にいない…どうすれば来てくれるのか」
「募集しても応募ゼロ、面接すら入らない」
「SNSを見ていると、みんな“会社員”以外の働き方ばかりに見える」
このようにお考えではないでしょうか?
結論から言うと、若者の人手不足時代に企業が実践すべき対応策は以下の通りです。
| 対応策 | 目的 |
|---|---|
| オンライン採用に注力する | 応募のハードルを下げ、接点を増やす |
| 中小企業は福利厚生を充実させる | 中小企業でも選ばれる環境をつくる |
| 地方企業はUIターン促進を活用する | 地方でも若者を呼び込める体制を整える |
| 育成前提で未経験者を積極採用する | 経験者頼みから脱却する |
| 外国人材の採用ルートを開拓する | 労働力の多様化に対応する |
| 高齢者・主婦層を柔軟に受け入れる | 若者だけに頼らない構造づくり |
| 副業・兼業人材を戦力にする | 短時間の稼働でも即戦力に |
| 職場体験やインターンでミスマッチを減らす | ミスマッチの防止と接点の創出 |
| 理念共感型の採用コンテンツを発信する | 働く意味を重視する若者に届く採用へ |
| 業務を一部自動化・省力化する | 人手不足を根本から補う仕組みづくり |
本記事では、若者が来ない理由を整理しつつ、企業が実践すべき10の対応策を具体的に解説していきます。
さらに、若手確保に成功した企業の具体事例や、定着率を上げる職場づくりのヒントも紹介。
この記事を読めば、若者が採用できない理由が理解でき、自社で今すぐ取り入れられる対策がわかります。
ぜひ最後までご覧ください。
24時間 無人で運営可能
国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し
- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応
- テック業界初!3つの物体識別方式を統合
人手不足の今、若者はどこへ?雇用が分散している3つの理由
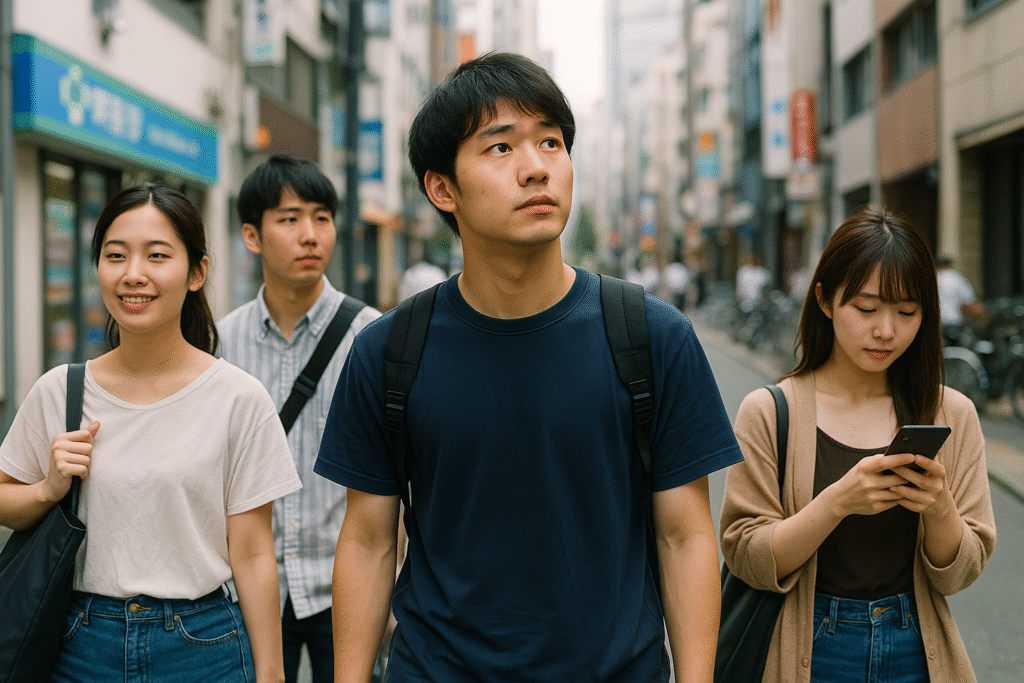
本章では、人手不足の今、若者の雇用が分散している3つの理由を解説します。
- 副業・兼業・スキマ労働で分散している
- 海外や都市部へのキャリア移動が加速している
- SNSやYouTubeなどの「個人メディア就業」が増えている
副業・兼業・スキマ労働で分散している
若者の働き方は大きく変化しており、かつての「正社員一択」ではなく、自分のペースで収入を得る方法を選ぶ方が増えています。
代表的な働き方の特徴を整理すると、以下の通りです。
| 働き方 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 副業 | 本業に加えて、別の仕事を掛け持ちする | 平日は会社勤務+週末に動画編集 |
| 兼業 | 複数の仕事を同時にこなす | 平日はフリーランス+夜にアルバイト |
| スキマ労働 | すき間時間を使って働く | 午前中だけカフェ勤務+夕方に配達 |
このように、自分で働く量・場所・時間を選べるスタイルが主流になってきています。
「会社に毎日通って8時間働く」ことに魅力を感じない若者にとっては、自由な働き方のほうが理にかなっていると感じるのです。
海外や都市部へのキャリア移動が加速している
若者が「地元にとどまる」という前提も、すでに過去のものになりつつあります。
都市部や海外を選ぶ理由は、次のように整理できます。
| 移動先 | 主な理由 | メリット |
|---|---|---|
| 都市部(東京・大阪など) | IT系や成長企業が多く、選べる仕事が多い | スキルアップしやすい/年収も上がりやすい |
| 海外 | グローバル志向の人が増えている | 語学・文化・自由度などを求める傾向 |
また、リモートワークの普及で「どこに住んでも仕事ができる」時代になりました。
地方企業としては「優秀な方ほど地元に残らない」という課題を抱えやすくなっているのです。
SNSやYouTubeなどの「個人メディア就業」が増えている
企業に就職せず、好きなことをネットで発信して収入を得る若者も増えています。
いわゆる「インフルエンサー」や「クリエイター」と呼ばれる方たちです。
主な活動例は次の通りです。
| 媒体 | 活動内容 | 収入の例 |
|---|---|---|
| YouTube | ゲーム実況や趣味紹介の動画配信 | 広告収益/企業タイアップ |
| ファッション・美容の投稿 | フォロワーに向けた商品紹介収入 | |
| TikTok | ショート動画でエンタメ発信 | 投げ銭や企業案件など |
「会社に入るのがイヤ」ではなく、「自分で仕事を作れる手段が増えた」というのが本質です。
企業のルールや上下関係に縛られず、自分の裁量で働ける環境に魅力を感じる若者が多いため、そもそも企業に就職しようと考えないケースも珍しくありません。
【若者はどこへ?】人手不足時代の企業が実践すべき対応策10選
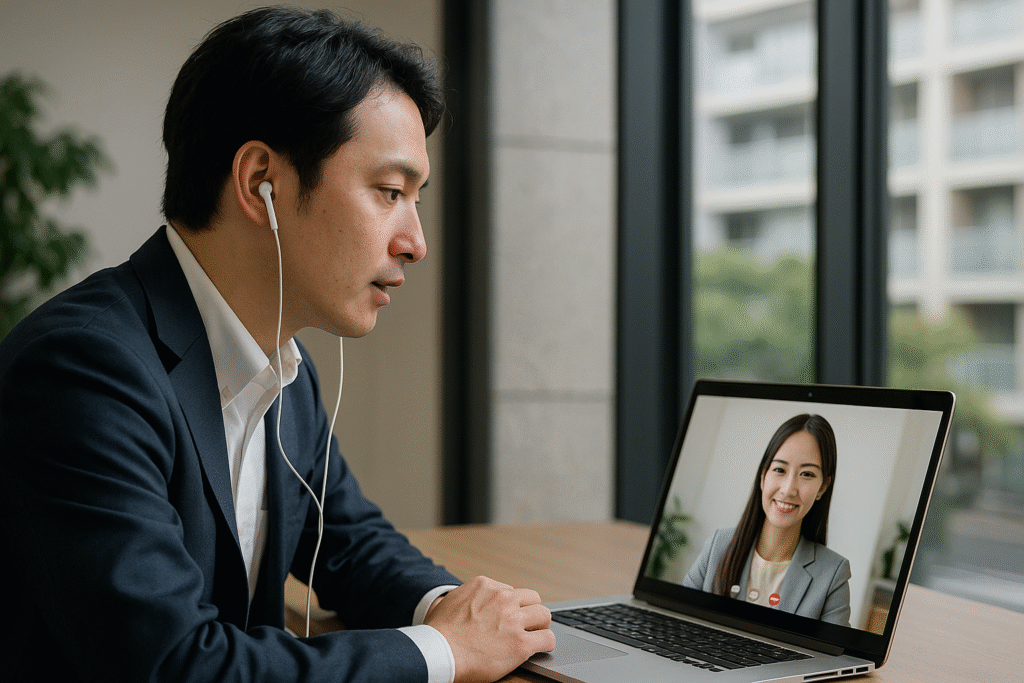
本章では、人手不足時代の企業が実践すべき対応策を10個紹介します。
- オンライン採用に注力する
- 中小企業は福利厚生を充実させる
- 地方企業はUIターン促進を活用する
- 育成前提で未経験者を積極採用する
- 外国人材の採用ルートを開拓する
- 高齢者・主婦層を柔軟に受け入れる
- 副業・兼業人材を戦力にする
- 職場体験やインターンでミスマッチを減らす
- 理念共感型の採用コンテンツを発信する
- 業務を一部自動化・省力化する
オンライン採用に注力する
ネットで情報を得られない会社は、「なんだか不安」と思われてしまうため、オンライン上で接点を持つための採用施策が欠かせません。
オンラインでできる採用活動の例は以下の通りです。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| 採用サイトの整備 | 写真や動画を活用して、職場の雰囲気や働く人の様子をわかりやすく伝える |
| SNSの活用 | Instagram・Xなどで、社員の日常や企業の価値観を発信し、親近感を持ってもらう |
| オンライン説明会 | Zoomなどで実施することで、遠方の求職者でも気軽に参加できるようにする |
中小企業は福利厚生を充実させる
給与や知名度で勝負しにくい中小企業こそ、「働きやすさ」を支える制度を整えることで若者に選ばれる存在になれます。
若手に支持されやすい福利厚生の例は、以下の通りです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 食事補助 | お弁当支給・ランチ代補助など、食費の負担を軽減できる制度 |
| 交通費支給 | 通勤にかかる費用(電車・ガソリン代など)を会社が負担 |
| 住宅支援 | 家賃補助や引っ越し費用の一部負担など、生活面のサポート |
| 特別休暇 | 誕生日やリフレッシュのための特別休暇を設ける |
| メンタルケア制度 | カウンセリングの機会を設け、心の健康も守る体制を用意 |
「この会社は社員の生活までちゃんと考えてくれている」と感じてもらえることが重要です。
地方企業はUIターン促進を活用する
地方企業は、Uターン・Iターン支援制度を活用することで、都市部の若者と接点を持ちやすくなります。
主な支援制度の内容は以下の通りです。
| 支援策 | 内容 | 企業側の活用ポイント |
|---|---|---|
| 引っ越し・家賃補助 | 地方移住にかかる初期費用(引っ越し代・家賃など)を一部自治体が補助 | 移住希望者に制度を紹介し、金銭面の不安を和らげる |
| 求職支援窓口 | ハローワークや自治体のマッチング支援機関を通じた求人紹介・相談対応 | 専門窓口に求人を出して、都市部の若者と接点を持つ |
| 地元インターン制度 | 学生や若手が地域企業で短期就業体験できる制度。交通費や宿泊補助が出ることも | インターン受け入れを通じて、実際の職場や暮らしを体験してもらう導線にする |
育成前提で未経験者を積極採用する
経験者にこだわらず、「これから育てる前提」で採用する企業ほど、若手が集まりやすく、定着率も高まりやすい傾向があります。
未経験者を受け入れるための主な工夫は以下の通りです。
| 工夫内容 | 具体的な取り組み例 |
|---|---|
| わかりやすいマニュアルの整備 | 写真や図解を使って仕事の手順を視覚的に説明。紙・動画マニュアルを用意して新人でも自己学習しやすくする |
| OJT(現場指導)の強化 | 教える担当者を明確にし、「見て覚える」ではなく隣で一緒にやってみせる形式で段階的に実務を任せていく |
| 安心できる職場づくり | 失敗を責めない風土を全員で意識し、「質問しやすい雰囲気」「褒めて育てる声かけ」など心理的安全性を高める工夫をする |
外国人材の採用ルートを開拓する
人手不足が深刻な中、日本人だけに限定せず、意欲のある外国人材を採用対象に加えることで、確保できる人材の幅が大きく広がります。
以下の方法を組み合わせることで、外国人材の採用と定着をスムーズに進められます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 外国人専門の人材会社を活用する | ビザ取得の手続きや求人票の翻訳、文化理解まで一括支援してくれるため、初めてでも安心 |
| 公的制度を活用する | 「技能実習」や「特定技能」などの制度を使えば、合法かつ明確なルールで外国人を受け入れられる |
| 社内の受け入れ体制を整備する | 日本語研修や生活相談、住宅サポートなどを用意し、働きやすく安心できる環境を整えることで定着率が向上 |
高齢者・主婦層を柔軟に受け入れる
若手の採用が難しい今、高齢者や主婦の方に活躍してもらえる仕組みを整えることも、現場の人手不足を補う一つの手段です。
しかし、実際には「働きたい意欲はあるのに、条件が合わず働けない」という声が少なくありません。
一律の働き方を求めるのではなく、以下のように個々の事情に合わせることが大切です。
| 課題の背景 | 配慮すべき点 | 対応策の例 |
|---|---|---|
| 長時間の勤務が難しい | ・体力に不安がある ・家事・育児・介護と両立したい | 1日3時間・週2日から勤務可能な短時間シフトを導入する |
| 通勤が困難 | ・車の運転が不安 ・交通手段が限られている | 在宅勤務や、徒歩圏内の人を対象にした「ご近所採用」を行う |
| 突発的な休みに対応しにくい | 子どもの体調不良や親の介護などで、直前に休まざるを得ないことがある | 当日欠勤OKなチーム制や、互いにカバーできる交代制シフトを整備する |
副業・兼業人材を戦力にする
フルタイムでは働けなくても、スキルを持った即戦力人材が副業・兼業という形で働くケースが増えています。
企業が受け入れやすくするための活用例は以下の通りです。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| デザインの発注 | 副業のクリエイターにロゴやHP制作を依頼 |
| 部分的な業務指導 | 週1回だけ業務改善コンサルとして来社 |
| 技術支援 | フリーのエンジニアに一部開発を依頼 |
「正社員にして全部やってもらう」よりも、「得意な部分だけ頼む」スタイルが、今の働き方に合っています。
職場体験やインターンでミスマッチを減らす
「入ってみたら思っていたのと違った」と辞めてしまう若者が多い中、実際に体験してから選んでもらう採用フローが効果的です。
具体的な導入例は以下の通りです。
| 体験制度 | 内容 |
|---|---|
| インターンシップ | 学生が夏休みに1週間だけ就業体験 |
| オープンワーク | 応募前に1日だけ職場見学・業務体験 |
| プレ雇用体験 | 数日だけ試しに働いてから判断できる制度 |
体験を通じて仕事内容や社内の空気を知ってもらうことで、「入ってすぐ辞める」リスクを減らせます。
理念共感型の採用コンテンツを発信する
「お金のためだけでは働きたくない」と考える若者には、企業の考えや姿勢そのものが届く採用コンテンツが有効です。
伝え方の工夫としては、以下のような施策があります。
| 発信施策 | 内容 |
|---|---|
| 社長インタビュー動画 | どんな想いで事業をしているかを伝える |
| ミッション掲載 | 会社の「存在理由」や社会的な役割を明記 |
| 社員ストーリー記事 | 現場で働く社員のリアルな声を届ける |
「どんな会社か」よりも「なぜこの仕事をしているのか」に共感する方が増えている今、理念に惹かれて入社した方は長く働く傾向もあるため、共感を軸にした採用は成果につながりやすいです。
業務を一部自動化・省力化する
人手が足りない現場では、「人を増やす」よりも「やらなくていい作業を減らす」工夫が効果的です。
代表的な自動化・省力化ツールは以下の通りです。
| ツール | できること |
|---|---|
| 勤怠アプリ | 出勤・退勤の記録をスマホで管理 |
| クラウド在庫管理 | 在庫の変動を自動で記録・発注できる |
| 書類作成ツール | 入力データから見積書や請求書を自動作成 |
こうしたツールを取り入れれば、1人あたりの業務負担を大幅に減らせます。
「人で埋める」から「ムダを減らす」へ発想を切り替えることで、根本的な人手不足対策になるでしょう。
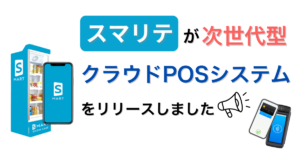
若者の人手不足で深刻な影響が出ている業界とは

本章では、若者の人手不足で深刻な影響が出ている3つの業界を紹介します。
- 建設・運輸業界|2024年問題で構造的に人手不足
- 医療・介護業界|高齢化と供給不足が重なっている
- IT業界|DX人材の奪い合いが続いている
建設・運輸業界|2024年問題で構造的に人手不足
建設・運輸業界では、2024年から「残業時間の上限規制」が始まったことで、人手不足が一気に加速しています。
背景と現場の変化をまとめると、以下の通りです。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 働き方の変化 | 長時間労働ができなくなり、稼げなくなった方が離職 |
| 労働力の減少 | 若手が入ってこない一方で、ベテランが定年で退職 |
| 業務の圧迫 | 作業量は変わらないのに、対応できる人数が減った |
たとえば、建設現場では「工期が遅れる」、トラック業界では「荷物が届かない」といった影響が目立っています。
医療・介護業界|高齢化と供給不足が重なっている
高齢者が増えてサービスの需要は拡大しているのに、支える側の若手が増えないことで、医療・介護業界は深刻な供給不足に直面しています。
問題を整理すると、次のようになります。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 働き手の不足 | 看護師・介護士などの人数が明らかに足りていない |
| 離職の連鎖 | 残ったスタッフに負担が集中し、体力的・精神的に限界 |
| 若手が敬遠 | 「大変そう」「給料が低い」と感じて応募すらしない層が多い |
その結果、介護施設では「入居を断らざるを得ない」ケースや、病院では「人手が足りず診療制限」されることも出てきています。
IT業界|DX人材の奪い合いが続いている
DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中、IT業界ではエンジニアなどの若手人材をめぐる争奪戦が続いています。
業界で起きている問題は以下の通りです。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 企業のニーズ急増 | あらゆる業種で「IT人材がほしい」と採用競争が過熱 |
| 育成の遅れ | 学校教育や現場の研修が追いつかず、人材供給が間に合わない |
| 地方企業の苦戦 | 高スキル人材が都市部に集中し、地方は取り残される |
たとえば、「業務を自動化したい」「クラウドで管理したい」と思っても、それを実現できる方がいないために、改善したくても動けない企業が増えています。
若者の人手不足が原因で生じる5つの弊害

本章では、若者の人手不足が原因で生じる5つの弊害を解説します。
- 採用コストが高騰する
- 従業員の離職率が上がる
- 接客に余裕がなくなり、サービスの質が下がる
- 業務を縮小・停止せざるを得なくなる
- 倒産リスクが上がる
採用コストが高騰する
若者の応募が減るほど、採用1人あたりにかかるコストは高くなります。
企業同士の人材争奪戦が激しくなることで、広告や紹介費が跳ね上がってしまうのです。
採用にかかる主なコストを整理すると、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 求人広告費 | 約20万円/月 |
| 人材紹介手数料 | 年収の30%前後(例:300万円なら90万円) |
| 選考費用 | 説明会・面接会場・交通費・宿泊費など |
これまで10万円で済んでいた採用が、今では50万円以上かかることも珍しくありません。
お金をかけても応募がなければ、「高コスト・低成果」という最悪の状況になってしまいます。
従業員の離職率が上がる
若手が入らない分、今働いている方に負担が集中してしまい、「もう無理…」と退職する方が増える状況が各地で起きています。
実際に現場で起きやすい問題をまとめると、次のようになります。
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 残業の増加 | 定時で終わらず毎日遅くまで働かされる |
| 休みが取りづらい | 代わりがいないため、連休や有給が取りにくい |
| 教える人がいない | 新人が来ないため、自分の成長が止まると感じる |
中堅やベテランが辞めてしまえば、業務の質も崩れていきます。
若者が足りないだけでなく、「今いる人もいなくなる」悪循環が進んでしまうのです。
接客に余裕がなくなり、サービスの質が下がる
人が足りなくなると、目の前のお客様にじっくり向き合う余裕がなくなり、サービス全体のレベルが落ちてしまいます。
起きやすい具体例を以下にまとめました。
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 待ち時間の増加 | 飲食店や病院で「呼ばれない」「来ない」状態が続く |
| 対応の雑さ | 商品の説明や案内が省略されてしまう |
| クレーム対応の悪化 | ミスに気づけず、怒られても改善が追いつかない |
スタッフが1人足りないだけで、「店の雰囲気がギスギスして見える」「会話が機械的」と感じる方もいます。
顧客体験が悪化すれば、リピーターが減り、売上にも直結してしまうでしょう。
業務を縮小・停止せざるを得なくなる
採用できない状態が続くと、既存の業務を回すので精一杯になり、「本当はやりたいことがあるのに、着手できない」「今ある業務すら維持できない」という状況に陥りがちです。
人手不足によって、実際に縮小・停止を余儀なくされるケースを以下にまとめました。
| 影響が出る業務領域 | 具体的な影響内容 |
|---|---|
| 営業時間の短縮 | 飲食店が夜営業をやめて昼営業のみに変更、週末を定休日にするなど営業時間を限定するケースが増加 |
| 生産ラインの停止 | 製造現場で作業員が確保できず、一部製品の製造を断念・注文受付を制限するといった対応を余儀なくされる |
| サービス展開の延期 | 新店舗オープンや新サービスの開始を予定していたが、人員不足でスケジュールを後ろ倒しせざるを得ない |
「人を入れて事業を拡大したい」と思っても、現場の体制が整わないまま先送りになる企業が増えてしまいます。
倒産リスクが上がる
人が集まらない状況が長引けば、売上の低下や経費の増加が続き、最終的に倒産につながるケースも出てきます。
実際に起こるリスクを以下にまとめました。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 売上の低下 | サービス提供が不安定になり、顧客が離れる |
| 業務の遅延 | 配送・製造が遅れて取引先からの信頼も低下 |
| 後継者不在 | 採用できないまま経営者が高齢化し、廃業を選ぶ |
「人がいないから閉めます」という貼り紙を見たことがある方もいるのではないでしょうか。
人手不足は、企業経営そのものを揺るがす深刻な経営リスクとして認識しておく必要があります。
若者の人手不足解消に成功した3つの事例

本章では、若者の人手不足解消に成功した3つの事例を紹介します。
- 株式会社保志|若手人材の継続雇用に向けた社内風土改革
- 株式会社大起産業|定着支援金で新卒の離職率ゼロ
- 株式会社島ごころ|若者が活躍できる環境づくりを推進
株式会社保志|若手人材の継続雇用に向けた社内風土改革
ベテラン中心の職場を“若手が活躍できる組織”へと生まれ変わらせたのが、株式会社保志の取り組みです。
実施された具体策は以下の通りです。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| 新卒採用の強化 | 高齢化対策として20代の積極採用を開始 |
| 訓練道場の設置 | 熟練者が技能を伝える実践型の教育施設を導入 |
| メンター制度 | 若手先輩社員が新入社員の業務と心のサポートを担当 |
| 女性の活躍推進 | 産休・育休後の復帰支援と柔軟な配属体制を整備 |
平均年齢が50代だった職場に、20代〜30代の社員が半数を占めるようになり、社内は一気に活気づきました。
株式会社大起産業|定着支援金で新卒の離職率ゼロ
「採った人がすぐ辞める」悩みを払拭したのが、大起産業の人材定着対策です。
離職率48%だった新卒者が、制度導入後はなんと0%を達成しました。
具体的な施策を整理すると以下の通りです。
| 施策 | 内容 |
|---|---|
| メンター制度 | 新卒に近い年齢の先輩が専属でサポート、週1回の面談を実施 |
| 担当手当の支給 | メンター社員には毎月手当を支給して意識を高める |
| 定着支援金の導入 | 新卒者に5年間毎月支給する金銭的インセンティブを設計 |
お金だけでなく、人のつながりによる安心感も重視したダブルサポート体制が、結果として「辞めない職場」を実現しています。
株式会社島ごころ|若者が活躍できる環境づくりを推進
「若者が来ないなら、まずは来てくれる人を受け入れる」という柔軟な発想で人手不足を乗り越えたのが、株式会社島ごころの事例です。
実際のアプローチは以下のように展開されました。
| 工夫 | 内容 |
|---|---|
| 採用対象の見直し | 高齢者や時短希望者など、幅広い働き手を受け入れ |
| 生産体制の改善 | 商品数を絞り、無理のない業務量に調整 |
| 組織づくり | リーダー育成や理念共有で社内の方向性を統一 |
最初から「若者を採ろう」と無理をせず、まずは受け入れ体制を整えることに集中した結果、最終的に若手の応募も自然と増えていきました。
若者の人手不足時代に求められる新たな採用戦略
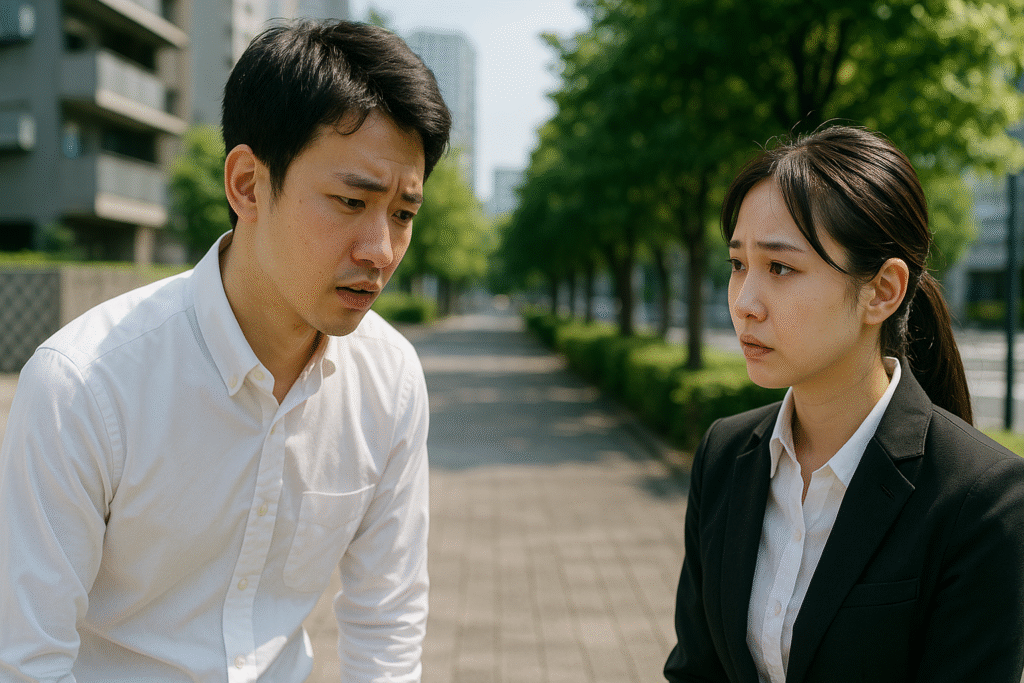
本章では、若者の人手不足時代に求められる新たな採用戦略を3つ紹介します。
- 採用のターゲットを明確にする
- 選考体験を改善して辞退を減らす
- 社内外からリファラル採用を活用する
採用のターゲットを明確にする
「誰でもいいから来てほしい」という姿勢では若手人材には響かないため、求める人物像を具体的に描くことが、採用成功の第一歩です。
採用ターゲットを絞るときは、次のようなポイントを明確にしましょう。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 年齢層 | 20代前半の第二新卒、大学卒業予定の新卒など |
| 性格や価値観 | チームで動くのが好き/変化を楽しめるタイプ |
| 経験やスキル | 未経験でもSNSが得意/接客アルバイト経験あり |
たとえば「人と話すのが苦手な人」ばかり応募してくる接客業や、「体力が必要なのに運動が苦手な人」を集めてしまう物流業など、ミスマッチは避けたいところです。
選考体験を改善して辞退を減らす
応募があっても、選考中に「やっぱりやめておこうかな」と思われたら意味がないため、選考体験を改善して辞退者を減らすことが大切です。
若者が不安を感じやすいポイントと改善策を整理しました。
| 不安の原因 | 受け手の印象 | 改善の例 |
|---|---|---|
| 返信が遅い | 「大事にされていない」 | エントリー後3日以内に連絡 |
| 雰囲気が見えない | 「怖いかも」「合わないかも」 | 面接時に社内写真や社員の声を見せる |
| 結果が曖昧 | 「モヤモヤが残る」 | 合否に関係なくフィードバックを送る |
たとえば、面接官が「笑顔なし・質問攻め」では、それだけで辞退につながってしまいます。
選考を“選別の場”ではなく“信頼を深める場”と捉える視点が必要です。
社内外からリファラル採用を活用する
紹介からの採用(リファラル)は、ミスマッチが少なく、定着しやすい採用手法として注目されています。
リファラル採用の強みと活用ポイントは以下の通りです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 信頼感のあるつながり | 社員の友人・知人から紹介されるため、会社の空気が事前に伝わる |
| 心理的ハードルが低い | 「知ってる人がいるから安心」と感じて応募しやすくなる |
| 定着率が高い | ギャップが少ない分、早期離職が起きにくい傾向あり |
たとえば「友達が楽しそうに働いている」と聞いて応募した方は、職場への理解も納得感も高いため、入りやすく続けやすいのです。
紹介制度を活性化させるためには、紹介者への感謝(報酬やメッセージ)を可視化することがポイントです。
【若者の人手不足時代】定着率を高める職場づくり施策
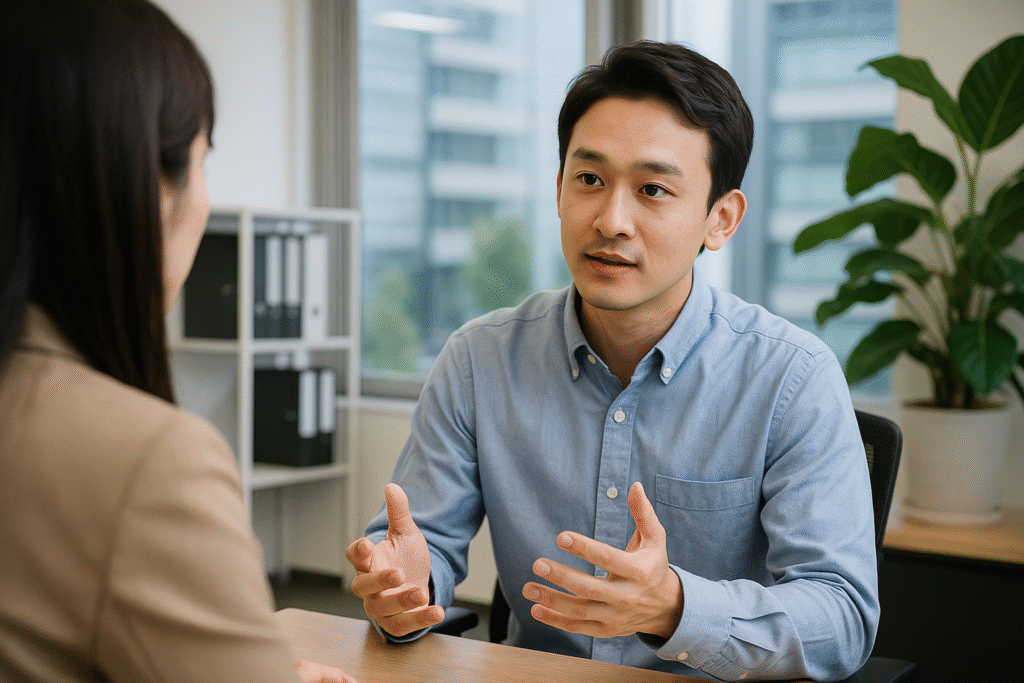
本章では、若者の人手不足時代に定着率を高める職場づくり施策を3つ紹介します。
- 心理的安全性を整える
- 人間関係のストレスを減らす
- 働きやすさが上がる制度を導入する
心理的安全性を整える
安心して「わからない」「困っている」と言える環境がある職場は、若手が辞めにくく、自発的に成長しやすい傾向があります。
心理的安全性とは何か、整えるために必要な行動を以下にまとめました。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 怒られない雰囲気 | 失敗や質問に対して否定せず、前向きに受け止める |
| 話しやすさ | 意見を遮らず、最後までしっかり聞く |
| 日常の会話機会 | 週1回の1on1(上司との個別面談)や雑談の場をつくる |
たとえば、「質問しただけで怒られる」「間違えると笑われる」と感じる職場では、若手は話すことすら怖くなってしまいます。
上司や先輩が「失敗しても大丈夫」と見せることが、挑戦する気持ちを引き出す土台になります。
人間関係のストレスを減らす
退職の理由で一番多いのは、「仕事内容」より「職場の人間関係に疲れた」という声です。
若手が感じやすいストレスと、改善のための取り組みを整理すると以下の通りです。
| ストレス要因 | 改善の工夫 |
|---|---|
| 話しかけにくい上司 | 年齢の近いメンター(相談役)を配置 |
| チームに入りづらい | 月1回のランチ会やレクリエーションを開催 |
| 批判や陰口が多い | 悪口禁止など、人を尊重する文化づくり |
たとえば「朝のあいさつが無視される」「いつも空気がピリピリしている」職場では、誰でも居心地が悪くなります。
小さな雑談や「ありがとう」の一言が増えるだけで、職場に“安心できる空気”が生まれます。
働きやすさが上がる制度を導入する
働き方に柔軟性がある職場は、「ここなら自分のペースで続けられそう」と思ってもらいやすくなります。
若者が定着しやすくなる制度の例は以下の通りです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| フレックスタイム制 | 出社時間を自分で調整できる仕組み |
| リモートワーク | 自宅や好きな場所で働ける環境づくり |
| 有給の取りやすさ | 周囲の理解があり、安心して休める雰囲気 |
| 家賃補助・副業OK | 生活や将来設計の自由度が広がる制度設計 |
たとえば「毎日同じ時間に出社して残業ばかり」より、「今日は午前に集中して午後はリフレッシュ」という働き方の方が、モチベーションも上がりやすくなります。
まとめ
本記事では、若者の人手不足に悩む企業がとるべき対応策について解説してきました。
それでは、この記事の要点を振り返ってみましょう。
- 若者は副業・個人活動・都市集中により雇用が分散している
- オンライン採用・福利厚生の強化で応募のハードルを下げられる
- 未経験者・外国人・主婦層など、受け入れの間口を広げることが効果的
- 理念発信やインターン制度でミスマッチを未然に防げる
- 建設・介護・IT業界では若者不足が業務縮小やサービス低下に直結している
- 採用難は離職率・倒産リスクの上昇にもつながる
- 制度・人材育成・風土改革によって定着に成功した企業事例が存在する
- リファラル採用・心理的安全性・柔軟な働き方が定着率改善に有効
本記事を参考に、自社の採用と定着の仕組みをアップデートしてみてください。