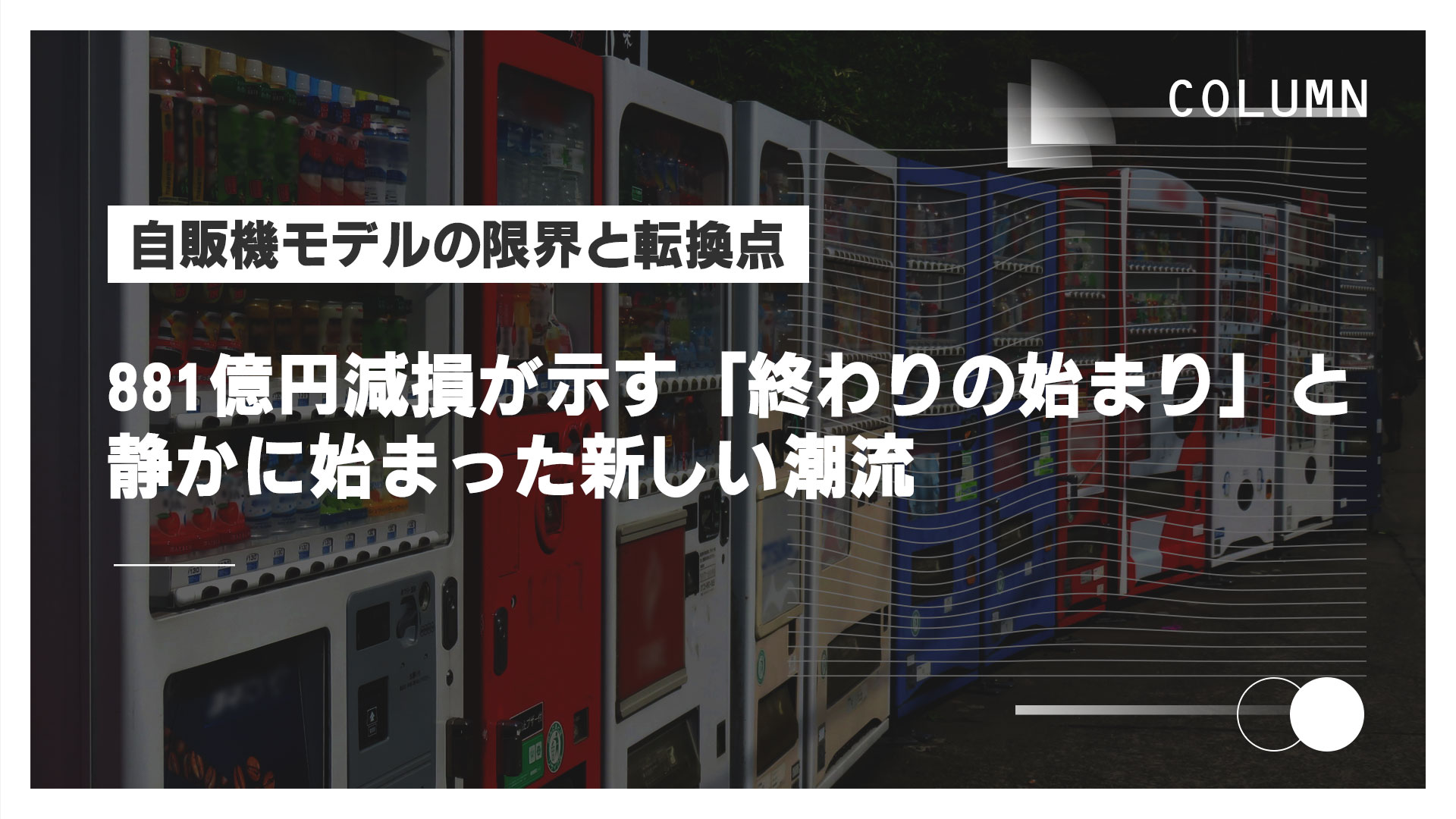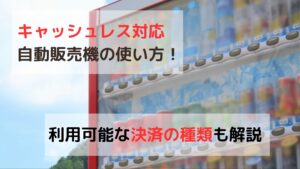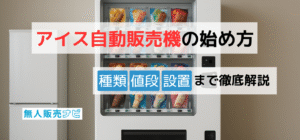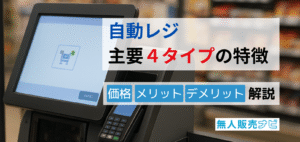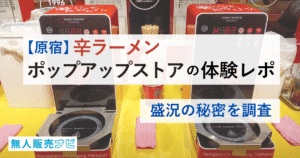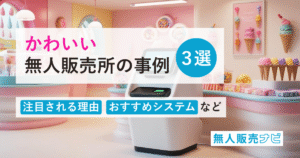日本の街角に並ぶ自動販売機。
どの時代の景色を切り取っても、そこには当たり前のように“赤いコーラの箱”があった。
しかしその風景は、今、大きな曲がり角に差し掛かっている。
かつて「置くだけで稼げる」と言われた自販機ビジネスが、
なぜここまで苦境に追い込まれているのか。
そして業界の巨人たちは、どこへ向かおうとしているのか。
そのヒントは、コカ・コーラが決算で突然計上した 881億円の減損 にある。
“売れれば儲かる”時代の終わり
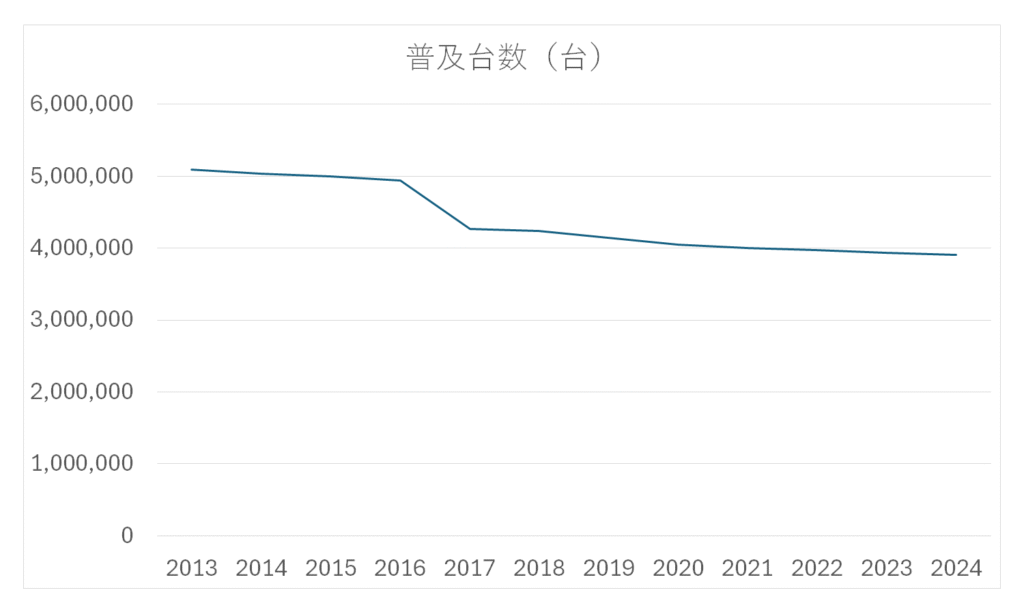
飲料自販機市場は、ここ10年で約17%も縮小した。
204万台——2024年の稼働台数は、ピーク時より40万台以上少ない。
この減少は、単なる景気や流行の話ではない。
もっと根の深い構造変化が起きている。
- スーパーやドラッグストアの「安い飲み物」へ人が流れる
- PB(プライベートブランド)の拡大
- 過去最高レベルの原材料高
- トラックドライバー不足による物流費の上昇
- 電気代の値上がり
- キャッシュレス非対応による機会損失
自販機は、固定費が重い。
電気代は24時間発生し、補充にはトラックと人手が必要だ。
つまり“ある程度売れなければ赤字”という性質が、
いまや“売れなければ即赤字”に変わってしまった。
コカ・コーラを襲った現実:自販機だけが明確に赤字

コカ・コーラBJHは2025年から、決算の区切り方を変えた。
飲料事業を「自販機」「小売・EC」「外食」の3つに分けたのだ。
すると、これまで見えなかった真実が一気に浮かび上がった。
- 小売・EC:しっかり黒字
- 外食:黒字
- 自販機:赤字
かつては最も稼いでいたチャネルが、今ではもっとも負担を抱える存在になっていたのである。
希望退職の募集、不採算機の撤去、そして八度にわたる値上げ。
それでも流れは変わらなかった。
そしてついに、会社は判断した。
「この事業の資産価値は、もう過去のものだ」と。
これが881億円の減損である。
しかし、これは“終わり”ではなく“準備”だった
減損は、過去を捨てる痛みを伴う処理だ。
だが同時に、未来に向けて身軽になるための行為でもある。
減損後は、減価償却費が年間80〜100億円も軽くなる。
これは、コカ・コーラが掲げた「2030年に事業利益800億円以上」という目標の裏側にある“布石”と言える。
もちろん、帳簿が軽くなってもキャッシュフローが自動的に改善するわけではない。
だからこそ同社は、別の方向で勝負を仕掛ける。
コカ・コーラの選択:「最適化」という地道な強化
コカ・コーラの戦略は一言でまとめると、
“自販機という現実を受け入れ、その中で勝つための徹底的な効率化”だ。
- AIで「補充量・補充タイミング」を自動計算
- 不採算機を分析し、撤去・移設
- ルート配送の最短化
- Coke ONの巨大データを使った需要予測
- 価格改定(=値上げ)で単価確保
自販機という枠組みは崩さず、
中身のオペレーションを徹底的に磨き込む方針である。
「景色を変えるのではなく、足元を固めて底上げする」——そんな戦い方だ。
サントリーは逆の道へ:「意味そのもの」を変える挑戦
一方でサントリーは、コカ・コーラとは全く違うアプローチを選んでいる。
彼らは自販機を
“飲料を売る箱”としてではなく、“企業の課題を解決する仕組み”
として再定義した。
- ボスマート(オフィス内ミニコンビニ)
- 社長のおごり自販機(社内コミュニケーション施策)
- 5分で後付けできるキャッシュレス端末
自販機を福利厚生ツールに変え、法人市場という新しいマーケットを開拓している。
サントリーの戦略は、
「枠組みごと作り替える」タイプの事業再設計
と言える。
そして、静かに頭角を現す“第三の選択肢”
コカ・コーラの「磨き込み」とサントリーの「作り替え」
この2つの道とは別に、近年急速に存在感を増しているモデルがある。
それがスマート販売機だ。
これは、従来の自販機とも、サントリーの法人モデルとも違う。
いわば“新しいカテゴリー”として誕生した存在である。
スマート販売機とは何か?

その特徴を簡単にまとめると、自販機の弱点を構造そのものから裏返した仕組みだ。
売れる商材が飲料に限定されない
- 惣菜
- 弁当
- 冷凍食品
- ギフト
- OEM商品 など
つまり、「本数勝負」ではなく「利益率」で戦える。
補充頻度が極端に少ない
飲料のように毎日補充する必要はない。
人件費は 1/2〜1/10 に。
キャッシュレス前提でトラブルがほぼゼロ
紙幣詰まり、硬貨管理、両替の必要なし。
運用が圧倒的に軽い。
データが蓄積し、店舗のように改善できる
どの商品が、どの時間に、どんな客層に売れたのか。
売場が“学習”し始める。
設置場所の幅が広い
- 企業
- 公共施設
- マンション
- 駅・観光地
- 農家の直売
など、飲料自販機とは違う市場を開拓できる。
スマート販売機は、
“飲料を売る機械”という思い込みを取り払い、小売そのものを再定義する存在になりつつある。
まとめ:自販機ビジネスは「どの未来を選ぶか」の時代へ
2025年の今、自販機ビジネスは3つの方向に分かれた。
1. コカ・コーラの徹底最適化
既存モデルを極限まで効率化し、地力を高める戦略。
2. サントリーの事業再設計
自販機の役割を「飲料販売」から「企業課題の解決」へ。
3. スマート販売機という新カテゴリー
飲料依存・固定費依存の構造から脱却した、全く新しい小売モデル。