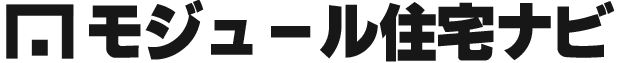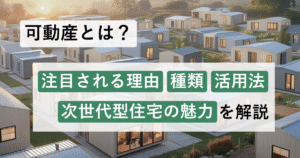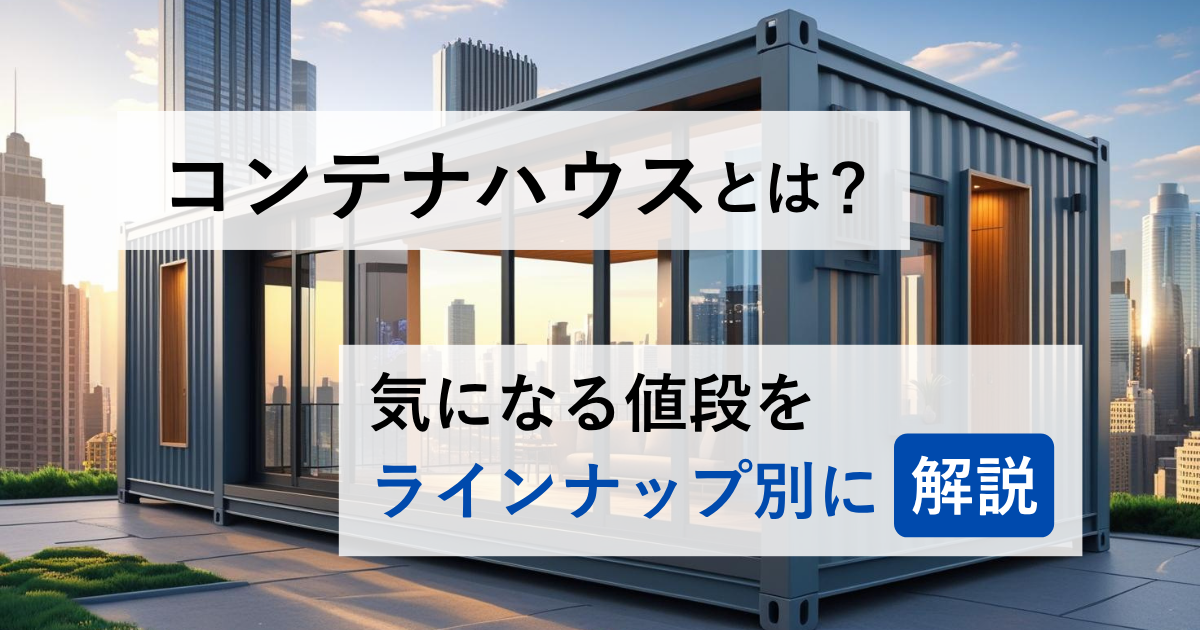
「コンテナハウスの値段って、実際いくらくらいなんだろう?」
「一人暮らし用の住宅や、風呂トイレ付きの快適な空間は作れるの?」
このようにお考えではないでしょうか?
コンテナハウスとは主に貨物輸送に使われる鉄製のコンテナを再利用、あるいはコンテナのような形状に設計して作られた建築物のことです。
この記事では、まずコンテナハウスについて以下内容を解説します。
- コンテナハウスのメリット&デメリット
- コンテナハウスのラインナップと気になる値段
- コンテナハウスに関するよくある質問(FAQ)
この記事を最後まで読めば、コンテナハウスに関するあらゆる疑問が解消され、あなたの目的や予算に最適な選択ができるようになります。
暮らし方に、もっと自由を
移動も拡張も、自由自在

- 即日設置、必要なときにすぐ住める
- 拡張自由、組み合わせて用途に対応。ニーズに合わせて柔軟に進化
- 電気、水道、排水等のインフラ接続可能
- 解体し、別の土地で再活用することも可能。捨てない住まいを実現
コンテナハウスとは|建築物としての役割と特徴
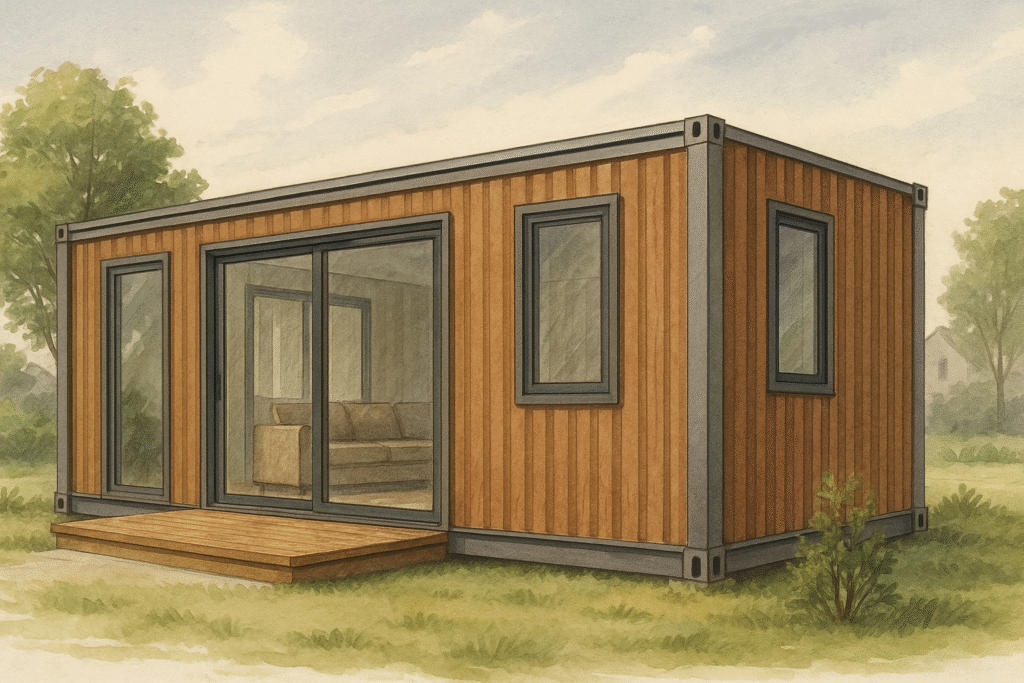
コンテナハウスとは、その名の通り、主に貨物輸送に使われる鉄製のコンテナを再利用、あるいはコンテナのような形状に設計して作られた建築物のことです。
近年、そのユニークなデザイン性や設置の手軽さから、さまざまなシーンで活用されるようになりました。
従来の建築物とは異なる特性を持ち、新しいライフスタイルやビジネスの可能性を広げる選択肢として注目されています。
ただし、コンテナを単に設置するだけでは建築物として認められず、日本の法律に適合させるための適切な設計と手続きが必要となります。
コンテナハウスの用途
コンテナハウスの用途は非常に多岐にわたります。
例えば、以下のような活用例が挙げられます。
- 個人住宅(一人暮らし、ミニマルな暮らし)
- セカンドハウス・別荘
- 店舗・カフェ・レストラン
- オフィス・事務所
- グランピング施設・ホテル
- イベント用の仮設ブース
- 災害時の仮設住宅
このように、コンテナハウスはその堅牢な構造とモジュール性を活かし、個人の住まいから商業施設、さらには社会的なインフラまで、幅広いニーズに応えられます。
組み合わせや内装の工夫次第で、オリジナリティあふれる空間を創造できる点も大きな魅力です。
建築基準法に適合する必要がある
日本国内でコンテナハウスを設置する場合、建築基準法における「建築物」として扱われます。
「建築物」とは、土地に定着する工作物で、屋根と柱、もしくは壁を有するものと定義されています。
コンテナハウスはこの定義に該当するため、設置の際は建築確認申請を行い、自治体の許可を得なければなりません。
建築確認申請の際は、建物の安全性(構造耐力、耐震性、防火性など)が法律の基準を満たしているかどうかが厳しく審査されます。
サイズは20ftと40ftが基本
コンテナハウスのベースとなる海上輸送用コンテナには、国際的に定められた規格サイズがあります。
一般的に使用されるのは、主に20フィート(ft)と40フィートの2種類です。
20ftコンテナの大きさは、長さ約6m × 幅約2.4m × 高さ約2.6mで、面積にすると約14㎡(およそ8〜9畳)の広さになります。
40ftコンテナは長さが約12mと20ftの倍あり、面積も約29㎡(およそ17〜18畳)と広々とした空間を確保できます。
これらのコンテナを単体で使うだけでなく、複数連結したり、積み重ねたりすることで、より広く複雑な間取りを実現可能です。
コンテナハウスを設置する主なメリット3つ
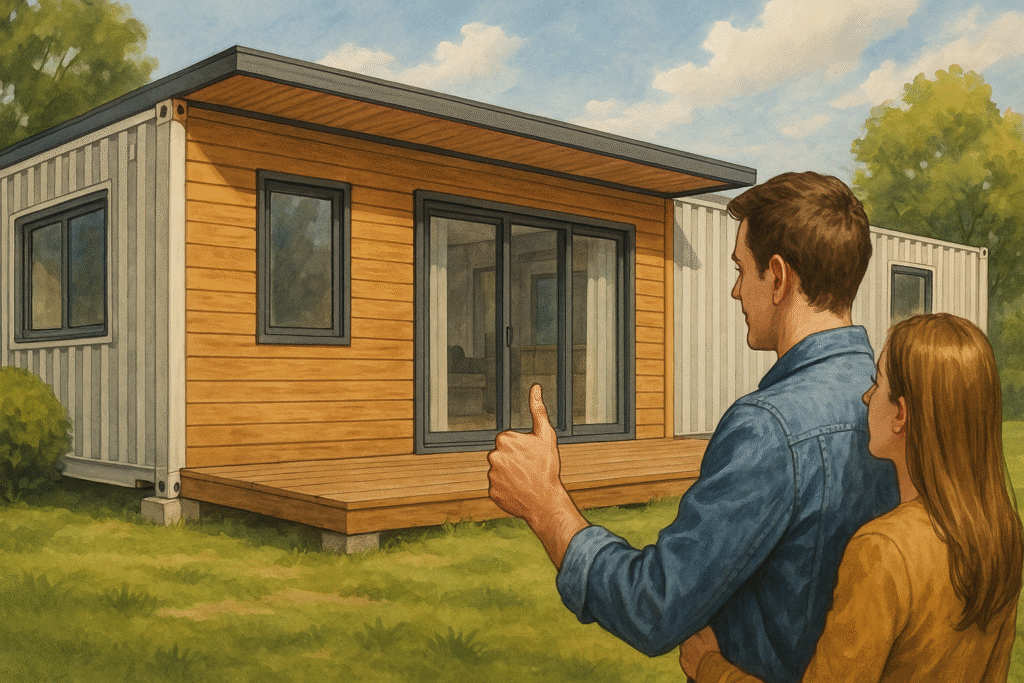
ここでは、コンテナハウスが持つ主な3つのメリットについて、具体的に解説していきます。
- 建築コストが比較的安く値段を抑えやすい
- 短期間で設置・施工が可能
- 一人暮らしやセカンドハウスなど用途に柔軟
建築コストが比較的安く値段を抑えやすい
コンテナハウスの大きな魅力の一つは、建築コストを比較的低く抑えられる点にあります。
工場で規格化されたコンテナをベースに製造するため、現場での作業が減り、人件費や材料費の削減につながります。
また、基礎工事も従来の木造住宅などと比べて簡素化できる場合が多く、全体の費用を圧縮しやすい構造です。
内装や設備、デザインにどこまでこだわるかによって総額は変動しますが、特に小規模な店舗やセカンドハウスを検討している場合、初期投資を抑えられる点は大きなメリットといえるでしょう。
短期間で設置・施工が可能
迅速に設置できる点も、コンテナハウスの特筆すべきメリットです。
多くのコンテナハウスは、基礎工事と並行して、工場で建物の大部分(躯体、内装、設備工事の一部)を作成可能です。
完成したユニットを現地に運び、設置・連結するだけで施工が完了するため、天候に左右されにくく、現場での作業期間を大幅に短縮できます。
事業を素早くスタートさせたい商業利用や、一刻も早い住まいの確保が求められる災害時の仮設住宅など、時間的な制約がある際に大きな強みとなります。
一人暮らしやセカンドハウスなど用途に柔軟
コンテナハウスは、柔軟な設計が可能で利用できる用途も幅広く、さまざまなニーズに対応可能なのが魅力です。
単体のユニットでコンパクトな一人暮らし用の住まいや書斎を作成できるほか、複数のユニットを組み合わせて広い居住空間や店舗を構築することも可能です。
L字型に配置してプライベートな中庭を作ったり、2階建てにして空間を立体的に活用したりと、アイデア次第でデザインは無限に広がります。
将来的に家族構成や事業規模が変化した際には、ユニットを追加して増築したり、逆に分離して移設したりといった対応も可能なため、ライフステージの変化に合わせた住まいづくりを実現できるでしょう。
コンテナハウスのデメリット・注意点3つ

多くのメリットを持つコンテナハウスですが、導入を検討する際には、事前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
特に、素材の特性に起因する課題や、法的な制約などが挙げられます。
- 断熱性や防音性に注意が必要
- 設置場所によっては法規制が課題
- 固定資産税の課税対象になる場合もある
断熱性や防音性に注意が必要
コンテナハウスの主な素材である鉄(鋼材)は、熱を伝えやすい性質を持ってるため、適切な断熱対策を施さないと、夏は暑く冬は寒い、過ごしにくい空間になってしまう可能性があります。
壁や天井、床に高性能な断熱材を充填したり、断熱性の高い窓を採用したりといった工夫が不可欠です。
また、鉄は音を反響させやすい性質もあるため、雨音や外部の騒音が気になることもあります。
快適な居住空間や静かなオフィス環境を実現するためには、断熱対策と合わせて防音・遮音対策にも注意を払わなければなりません。
設置場所によっては法規制が課題
コンテナハウスは建築基準法上の「建築物」にあたるため、設置には法的な制約が伴います。
まず、建築確認申請が必須であり、自治体の許可を得なければ設置できません。
さらに、土地には「都市計画法」によって用途地域が定められており、例えば「第一種低層住居専用地域」では店舗や事務所の建築が原則として禁止されているなど、建てられる建物の種類が制限されます。
また、接道義務(敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること)など、クリアすべき条件は多岐にわたります。
複雑な要素が多々あり、希望の土地にコンテナハウスを設置できるか否かを判断するうえでは、専門家への事前相談が不可欠です。
固定資産税の課税対象になる場合もある
土地に定着して設置されるコンテナハウスは「建築物」として扱われるため、一般の住宅と同様に固定資産税の課税対象となります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地や家屋などの固定資産に対して課される市町村税です。
税額は、固定資産税評価額に標準税率(1.4%)を乗じて算出されます。
「手軽に設置できるから税金はかからない」と誤解されがちですが、基礎工事を伴い、永続的に使用されるものは不動産と見なされます。
ランニングコストとして固定資産税がかかる点を念頭に置いたうえで、資金計画を立てましょう。
コンテナハウスのラインナップと気になる値段
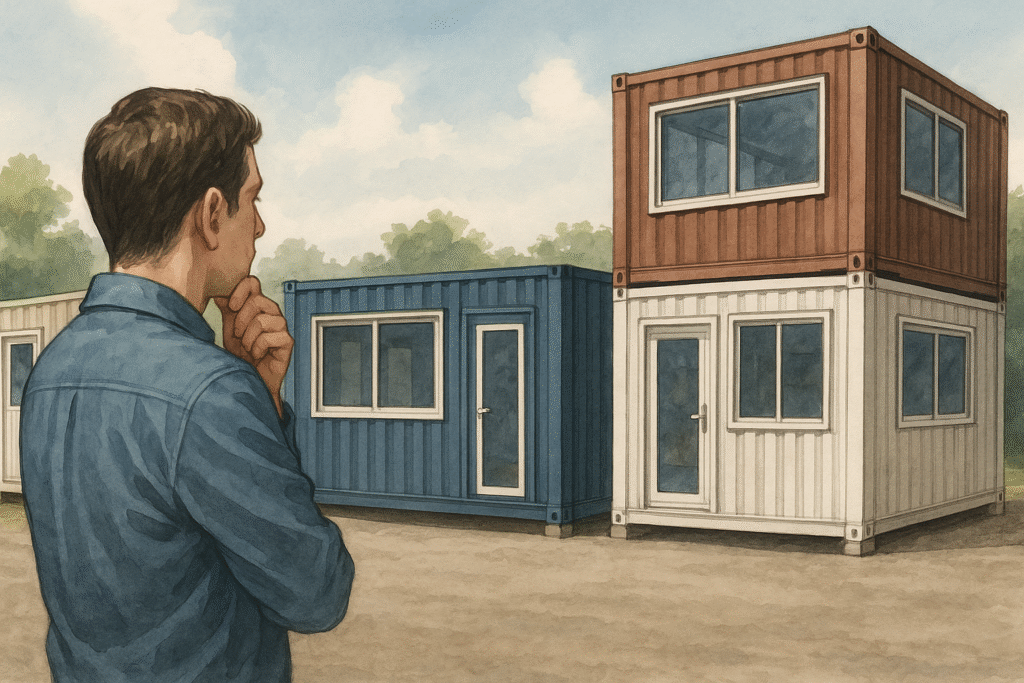
コンテナハウスの価格は、サイズ、デザイン、内装のグレード、設備の充実度などによって大きく変動します。
一般的なモデルの価格帯や、購入以外の選択肢について解説するので、導入を検討する際の目安として参考にしてください。
- 風呂トイレ付きの戸建てモデルの価格帯
- 2階建て+風呂トイレ付きモデルの価格帯と特徴
- 賃貸・レンタルで使う場合の料金目安と契約形態
風呂トイレ付き戸建てモデル【200~300万円】
風呂、トイレ、キッチンといった水回りを完備した居住用のコンテナハウスは、生活に必要な機能が一通り揃っており、住宅やセカンドハウスとして人気があります。
サイズや仕様によって価格は大きく異なりますが、本体価格の目安としては200万~300万円が一般的です。
また、本体価格以外にも下記のような費用がかかるため、事前に総額を把握しておくようにしましょう。
- 輸送費
- 設置工事費
- 基礎工事費
- インフラ(電気・水道・ガス)接続費用
内装や設備のグレードを上げる場合は、さらに費用が加算されます。
想定以上の出費となって後悔しないようトータルでかかるコストを正確に見積もったうえで検討しましょう。
2階建て+風呂トイレ付きモデル【1,000万円~】
コンテナを2階建てにすれば、限られた敷地面積でも居住空間を広く確保できます。
例えば、1階をリビングや店舗、2階をプライベートな居住スペースにするといった使い方が可能です。
2階建てモデルの場合、階段の設置や、上下階を安全に接続するための構造計算・補強工事が必要になるため、単層のモデルよりも価格は高くなります。
本体価格は1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
こちらも本体価格に加えて、輸送費や設置費、各種工事費が別途発生します。
デザインの自由度が高い分、費用も青天井になりやすいため、予算と希望のバランスを考えながら計画を進めめましょう。
賃貸・レンタルモデル【月額7万~20万円】
コンテナハウスは購入だけでなく、賃貸・レンタルでも利用可能です。
特に、イベントブースや建設現場もの仮設事務所など、一定期間のみ利用したい場合に適しています。
料金はサイズや期間、設備によって異なりますが、月額7万~20万円ほどでレンタルできる場合が多い傾向です。
契約形態は、短期から長期までさまざまで、初期費用を抑えて手軽に利用開始できるのがメリットです。
ただし、レンタル品はデザインや間取りの自由度が低く、新品ではない場合もあります。
用途や利用期間を考慮し、購入とレンタルのどちらが自身の計画にとって最適かを見極めたうえで検討しましょう。
マイクロシティのユニット住宅が選ばれる理由|従来のコンテナハウスを超える柔軟性

ここまで一般的なコンテナハウスについて解説してきましたが、その利便性をさらに進化させた新しい選択肢として、可搬型モジュール住宅「マイクロシティ」をご紹介します。
マイクロシティは、従来のコンテナハウスが持つ課題を克服し、スピード、品質、サステナビリティを兼ね備えた次世代のライフスタイル拠点です。
ここでは、マイクロシティが選ばれる理由を具体的に解説します。
- ユニットを組み合わせて構成する可搬型住宅
- 2〜3名で組立可能&最短1日で設置完了
- インフラのない場所でも使える自立型エコシステム
- 再設置・再利用が可能でサステナブルな設計
ユニットを組み合わせて構成する可搬型住宅
マイクロシティは、輸送用のコンテナを再利用するのではなく、初めから居住空間として設計されたパネルモジュール構造を採用しています。
パネルを組み立ててユニットを構成するため、輸送コンテナの規格に縛られない自由な設計が可能です。
例えば、L字型やコの字型、中庭のあるレイアウトも即時に構成できます。
これは、住まいを自由に、そして環境と共生することを目指すマイクロシティの基本コンセプトです。
家族構成や事業の変化に合わせてユニットの増減も容易にでき、まさに「動かせる家」として、未来のニーズに柔軟に対応します。
2〜3名で組立可能&最短1日で設置完了
マイクロシティの最大の特長は、その圧倒的な展開スピードです。
特別に設計されたパネルユニットは、クレーンなどの重機を使用せず、わずか2〜3名の少人数で組み立てが可能です。
そのため、狭小地や離島など従来は重機の搬入が困難で設置を断念せざるを得なかった立地でも、確実な施工を実現できます。
最短1日での設置も可能なため、災害発生時に迅速な住環境を提供したり、イベントや事業の機会を逃さずスピーディーに拠点を構えたりと、あらゆる場面で大きなアドバンテージとなります。
撤去も同様に1日で完了するため、土地の原状回復も容易で、一時的な利用ニーズにも柔軟に対応できます。
インフラのない場所でも使える自立型エコシステム
マイクロシティは、電気や水道などのインフラが未整備な場所においても機能する、完全自立型のエコシステムを構築できます。
各モジュールに搭載された太陽光パネルと蓄電池によって、電力の完全自給が可能なほか、独立した給排水システムや通信機器の活用で、快適な生活環境や事業運営を即座に開始できます。
山間部や海辺でのリゾート開発、グランピング施設の運営はもちろん、災害時における避難所の機能性を格段に向上させ、被災者の心身の負担を軽減可能です。
再設置・再利用が可能でサステナブルな設計
マイクロシティは、環境との共生を重視し、「使い捨てない住まい」をコンセプトに設計されています。
最小限の基礎工事で設置できるため、森林や海辺といった自然豊かな土地を傷つけず、景観に溶け込む拠点を築けます。
また、すべての部材は再設置・再利用を前提としているため、ライフスタイルの変化や事業の移転に合わせて、住まいを分解し、別の場所で再び組み立てることが可能です。
建物の解体に伴う廃棄物を大幅に削減し、環境負荷の低い持続可能な建築のあり方を実現します。

コンテナハウスに関するよくある質問(FAQ)
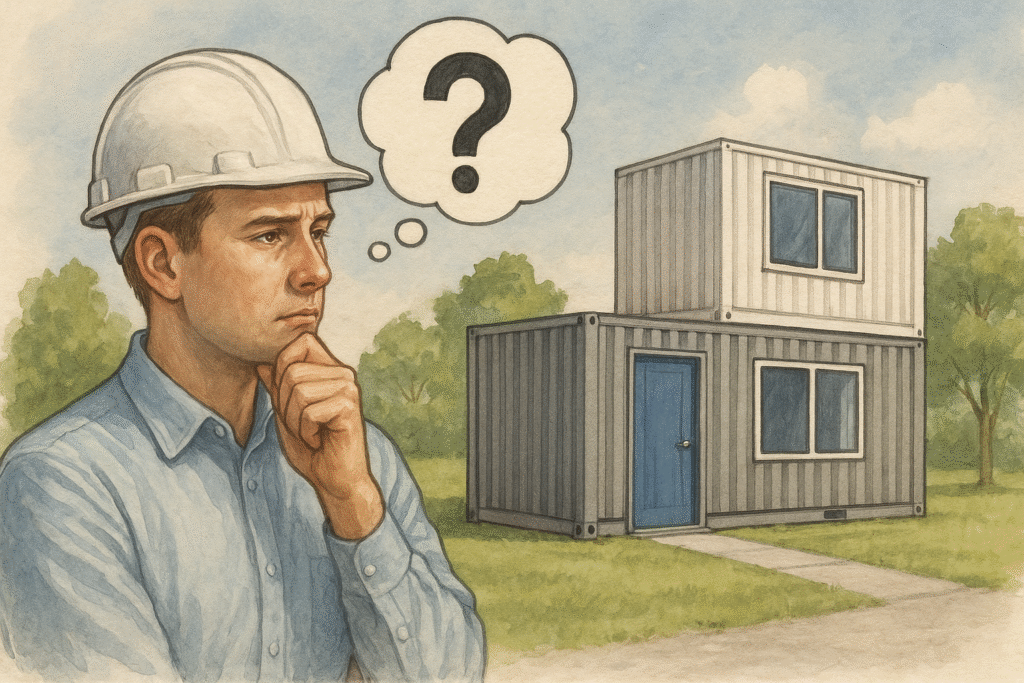
コンテナハウスに関するよくある質問を紹介します。
コンテナハウスの安全性はどうなの?
コンテナハウスの安全性は、建築基準法に準拠した設計と施工がなされているかどうかで大きく左右されます。
特に輸送用コンテナをベースにしている場合、日本の地震・台風など自然災害に耐えうる構造補強が不可欠です。
設計段階でしっかりと構造計算を行い、耐震性・耐風性を高めた仕様になっているかどうかを確認しましょう。
断熱性や遮音性など居住環境としての快適さも、長期的な安全・健康に直結するため、内装材や断熱材のグレードにも注目したうえでの検討が大切です。
コンテナハウスは移動もできるの?
コンテナハウスはもともと移動可能な構造を持っていますが、実際に移設するとなるとクレーンや大型トラックが必要となり、それなりの費用と手間がかかります。
また、移設先での再設置や基礎工事、インフラの再接続なども必要になるため、「動かせる家」とはいえ簡単に何度も引っ越せるわけではありません。
「移動できる=可変性が高い」というメリットはありますが、移設の現実的なコストと手間は事前に把握しておくべきです。
実際コンテナハウスに住んでみた人の声は?
実際にコンテナハウスに住んだ人からは、以下のような声がよく聞かれます。
- 「夏は暑く、冬は寒い」
- 「雨音が響く」
- 「断熱・遮音性に課題がある」
これらの課題は、鉄製のコンテナという素材特性によるもので、しっかりとした断熱対策・内装工事がされていないと発生しやすいです。
しかし、近年では高性能な断熱材や空調設備を導入するコンテナハウスも増えており、快適性の改善が進んでいます。
購入や設置を検討する際は、内装・設備の仕様をよく確認し、「仮の住まい」ではなく長く快適に暮らせる仕様かどうかを見極めることが重要です。
まとめ
本記事では、コンテナハウスの基本情報から気になる値段、メリット・デメリット、そして従来のコンテナハウスの概念を超える新しい選択肢について解説しました。
この記事の要点を振り返ってみましょう。
- コンテナハウスはコストを抑えやすく短工期で設置できるが、断熱性や法規制、固定資産税には注意が必要
- 風呂トイレ付きの住宅モデルや2階建てなど、用途や仕様によって値段は大きく変動する
- 従来のコンテナハウスの課題であった設置の手間やインフラ問題を解決する選択肢として、可搬型モジュール住宅「マイクロシティ」がある
- マイクロシティは最短1日で設置でき、インフラのない場所でも自立可能。再設置・再利用もできるサステナブルな設計が特徴
この記事を参考に、ご自身の目的やライフプランに合ったコンテナハウスの活用、あるいは「マイクロシティ」という新しい住まいの形の導入をぜひご検討ください。